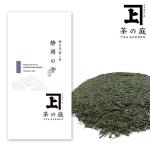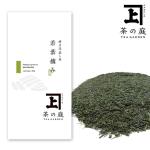八十八夜とは、日本の季節の移ろいを示す雑節の一つです。
立春から数えて88日目にあたり、春から夏へと季節が変わる大切な節目とされてきました。
この時期に摘まれる新茶は特に縁起が良いとされ、飲むと無病息災で過ごせると言い伝えられています。
この記事では、八十八夜がいつなのか、そして新茶を飲む風習の由来や縁起が良いとされる理由について、さまざまな角度から解説します。
目次
「八十八夜」とはいつ?立春から数えて88日目のこと
八十八夜は、二十四節気の立春を1日目として、そこから数えて88日目に当たる日のことを指します。
太陽の動きを基準にした二十四節気と違い、日付を数えるため毎年同じ日になるとは限りません。
立春の日付が年によって変動するため、八十八夜もそれに合わせて変わりますが、例年5月2日頃になります。
八十八夜は、二十四節気を補うために設けられた雑節の一つであり、季節の移り変わりをより細かく把握するための日本独自の暦です。
この時期は、気候が安定し始め、本格的な農作業シーズンの到来を告げる重要な日として、古くから人々の暮らしに根付いてきました。
昔から農作業の目安とされてきた季節の変わり目
八十八夜は、昔から農作業を始める上での重要な目安とされてきました。
「八十八夜の別れ霜」という言葉があるように、この日を過ぎると遅霜の心配がなくなり、気候が安定するといわれています。
そのため、農家の人々はこの日を境に、茶摘みをはじめ、苗代の準備や畑仕事などを本格的に開始する目安にしていました。
特に茶農家にとっては、一番茶の収穫時期であり、一年で最も忙しい季節の到来を意味します。
暦の上では夏の始まりとされる「立夏」も八十八夜の数日後に迎えることが多く、春から夏へと季節が移り変わる節目であることを示しています。
このように、八十八夜は農業に従事する人々にとって、作業計画を立てる上で欠かせない日でした。
八十八夜の新茶を飲むと縁起が良いとされる理由
八十八夜に摘まれた新茶を飲むと、縁起が良いと広く信じられています。
なぜそのようにいわれるようになったのでしょうか。
その背景には、古くからの言い伝えや、日付が持つ数字の縁起の良さ、そしてこの時期に収穫される茶葉自体の優れた品質が関係しています。
八十八夜の新茶が持つ特別な価値は、こうした複数の理由が重なり合うことで、日本の文化として深く定着していきました。
ここでは、それぞれの理由について詳しく見ていきます。

一年間を元気に過ごせるという言い伝えがある
八十八夜に新茶を飲むと縁起が良いとされる理由の一つに、「一年間を無病息災で過ごせる」という古くからの言い伝えがあります。
この時期に摘まれる一番茶は、冬の間に栄養を蓄えた茶の木から最初に芽吹いた新芽で作られます。
そのため、生命力にあふれ、栄養価が非常に高いと考えられてきました。
かつて医療が発達していなかった時代には、お茶は貴重な薬としても扱われており、その薬効への期待も大きかったと推測されます。
この栄養豊富な新茶を飲むことで、長寿や健康を願う風習が生まれたのです。
この縁起の良い言葉とともに、八十八夜の新茶を飲む文化は人々の間に広まり、現在まで大切に受け継がれています。
末広がりの「八」が重なる縁起の良い日だから
八十八夜という名称に含まれる「八」という数字も、縁起の良さと深く結びついています。
漢数字の「八」は、下に向かって形が広がっていく様子から「末広がり」を意味し、古来より幸運や繁栄をもたらす吉数とされてきました。
八十八夜は、この縁起の良い「八」が二つ重なる日であるため、非常にめでたい日と考えられています。
さらに、「米」という漢字を分解すると「八十八」になるという説もあり、米を主食としてきた日本人にとって、この日は五穀豊穣を願う特別な意味合いも持っていました。
このように、農業の節目であることに加えて、幸運を象徴する数字が重なる日であることから、八十八夜は特別な日として人々に認識されてきたのです。
栄養が豊富で上質な茶葉が育つ時期だから
八十八夜の頃に収穫される茶葉が、品質的にも栄養的にも非常に優れていることが、縁起の良さと結びつく科学的な理由です。
茶の木は、寒い冬の期間、じっくりと土壌から養分を吸収し、その力を蓄えています。
春になり暖かくなると、その蓄えられた栄養分が一斉に新芽へと送り込まれます。
このため、八十八夜前後に摘まれる一番茶には、旨みや甘みの成分であるテアニンが豊富に含まれており、苦み成分のカテキンは比較的少なめです。
その結果、まろやかで香り高い、上質な味わいのお茶になります。
栄養価の高さとおいしさを兼ね備えたこの時期のお茶を飲むことが、健康に良いとされ、縁起物として珍重されるようになったのです。
唱歌「茶つみ」にも登場する日本の風物詩
八十八夜は日本の文化に深く根付いた風物詩であり、その象徴的な存在が文部省唱歌の「茶つみ」です。
多くの人が一度は耳にしたことがある「夏も近づく八十八夜野にも山にも若葉が茂る」という歌い出しの歌詞は、まさにこの季節の情景を見事に描写しています。
この歌によって、八十八夜が初夏の訪れを告げる日であることや、茶摘みの季節であることが広く知られるようになりました。
歌詞に描かれているように、茜色のたすきに菅の笠をかぶった娘たちが茶摘みをする風景は、日本の原風景の一つとして多くの人の心に刻まれています。
この歌の存在が、八十八夜という言葉をより身近なものにし、季節の節目として楽しむ文化を後世に伝える役割を果たしてきました。

まとめ
八十八夜は、立春から数えて88日目にあたる雑節の一つで、毎年5月2日頃に訪れます。
この日は「八十八夜の別れ霜」といわれるように、気候が安定し始めることから、古くから茶摘みをはじめとする農作業の目安とされてきました。
八十八夜に摘んだ新茶を飲むと縁起が良いとされるのは、一年間を無病息災で過ごせるという言い伝えや、末広がりで縁起の良い「八」が重なること、そして冬の間に蓄えられた栄養が豊富な上質な茶葉が収穫できる時期であることなど、複数の理由が重なっています。
また、唱歌「茶つみ」の歌詞にも登場するように、初夏の訪れを告げる日本の風物詩として、文化の中に深く根付いています。